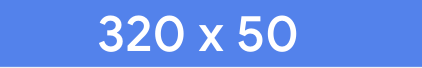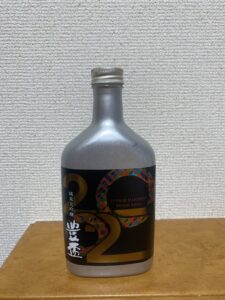二日目の朝、南紀は雨が降っていた。愛知よりは暖かいが、師走の朝は肌寒く、朝食も兼ねて立ち寄った勝浦漁港にぎわい市場の側にある足湯に浸かった。
市場の入口付近ではマグロのカマ焼きをしており、炭火の香りと熱気を漂わせていた。
私はその中の『市場ごはん しげ』にてマグロ刺身定食と、『雑賀屋』の『ついてる!唐揚げ』を食べた後、再び足湯に浸かりながら、雨の降り立つ港を眺めていた。
地上から蒸発した水分で雨雲が作られ、それが雨を降らせて地上に返ってくるというのは、地上と空のやり取りの様にも感じられた。その点では、雷も似たものかも知れない。地上からすれば、水を送ったら電気が返ってくるのは予想外だろうか。
雷の発生原理については諸説あるらしいが、下記の様な流れを私は聞いたことがある。
①太陽の日射によって、地表の湿った空気が暖められて上昇気流となり、上空で冷やされたそれが水滴となり、塊となって雲となる。
②上空で周囲の温度が氷点下に達し、雲の中に雨粒だけでなく氷の粒ができる。それがある程度大きくなり、上昇気流の力より重力が勝ると、今度は下降を始める。
③その氷の粒同士がぶつかり合い、小さな粒にはプラス電荷、大きな粒にはマイナス電荷が帯電する。
すると雲の上方にプラス電荷、下方にマイナス電荷が帯電し、それが続くと雷雲となる。
④静電気誘導作用により、雷雲下方のマイナス電荷に対応して、地表にプラス電荷が貯まる。
⑤雷雲の成長とともに電気の力も強くなり、プラス電荷とマイナス電荷が引き合おうとする中で、空気が電気の力に耐えきれなくなった時に絶縁破壊を起こして放電し、雷が発生する。
雷を手軽に発生させて発電する仕組みを、安全も確保した上で実用化することができれば、革新的なエネルギー問題や地球温暖化への対策になるのではなかろうか?こんな考えはきっと既に科学者達は既に検討中であろうが、ふと思いついて言いたくなってしまった。
ニュートリノ観測用のスーパーカミオカンデの様に、特殊な条件が揃った場所でないと難しいのだろうか、などと思いつつ、きっといつかは人類はそれを実現する時がくるのだろうなどと、小雨降る和歌山で友人を待つという状況に似合わないことを考えていた。

そうしている内にお昼になり、友人と合流することができた。彼は大阪から来ており、特急くろしおを使ってきた。車で来るのであれば、大阪からの方が距離が短いが、特急のルートは大阪からの場合は紀伊半島の西側をぐるりと周ってくる必要があり、所要時間は名古屋からの特急南紀の方がやや短かった。
彼も那智に来たからには先ずはマグロが食べたいということで、『まぐろ料理 竹原』にて、王道のマグロ定食を食べた。
朝に食べたものとは違い、こちらは見た目通りに、より赤身の味わいが強かった。部位の違いも間違いないが、マグロの種類も違っていたことだろう。マグロの違いを細かく認識するには、味覚の鋭さも種類の知識も足りないが、こちらは一部、クロマグロが入っていたと思われる。
初日の昼から2日目の昼まで、全ての食事でマグロを堪能するという、マグロ尽くしの食生活に喜びを実感した。前回に来られなかったことの心残りの3割程は、これで満たせたと言っても過言ではないが、それだけに残りの7割にも期待が膨らんだ。

昼食後は、バスで熊野那智大社を訪れた。バス停から歩いて那智大社を周り、那智の滝を眺めたりなどして、参詣はそれなりにハイキングとしてちょうど良い運動だった。
帰り道では野生の鹿が山中だけでなく、住宅の裏地にも数頭おり、声をかけたら反応はしたが、10m程度のところからでは逃げる素振りはなかった。奈良公園や厳島の鹿程ではないにせよ、人に慣れているのだろう。
私は厳島の鹿が観光客の持っていたパンを引ったくる姿や、飲食店に入っていこうとする姿を何度か目撃している。後者は押しボタンドアの仕組みが分からずに未遂に終わっていたが、何とも逞しいものだ。人との関係に適応して行きていく、これも進化に違いない。
そしてこれは後で知ったのだが、那智の滝は熊野那智大社ではなく、滝の真正面にある飛瀧神社が祀っている御神体だそうだ。
私は未だ神様をしっかりと視認もしくは知覚したことはないが、これだけの落差のある滝には、確かに神様が宿っていてもおかしくはないのかも知れない。
この滝を見て、ここに社を建てた人は何を感じたのだろうか。また、自然のものに神様が宿る、という共通認識の様なものがなかったであろう時代に建てられたのか、あるいは?

夕方になり、いよいよ今回の旅の最終目的地へと向かうべく、新宮からのバスで川湯温泉へと向かった。
しかし、そのまま直行するのではなく、フリーパスを活用して途中の下地橋バス停で下車した。この旅の一つの目玉イベントとして、下地橋バス停の直ぐ側にある『鶏そば 下地橋』を訪れる為だ。
時刻は16:30頃。開店の約30分前に到着し、券売機で券を購入して入店可能時間を待った。
ここも前回、特急が運休になって私は来られなかったが、友人は行けた店であり、彼からとても美味しいと聞いていた。今回こそはその後悔を晴らし、存分に楽しみたいと期待を込めていた。
先ずは1杯目。友人はスタンダードの鶏そばを注文し、私は目に付いた熊野牛醤油を注文した。
1杯目は基本的なものにしようと思っていたものの、熊野牛についつい目を惹かれて頼まざるを得なかった。今回の日程的にも、熊野牛を食べられるのはここしかないと言うのも一つの理由ではあった。
2枚程の大きな肉の乗った醤油ラーメンで、醤油の塩味に熊野牛の脂の甘みが程良く絡み、スープだけでいくのも、麺と絡めていただくのもやみつきになる様だった。
牛肉の脂が醤油ラーメンによく合うのは、牛肉の時雨煮が美味しいことを思えば納得であった。ご飯が欲しくなるのもまた同様で、餃包セットを注文してご飯を混ぜつつスープを飲み干した。
1杯目からかなり幸せになれたが、折角の二人旅ということで、一人では食べ切れない、もしくは試したいメニューを注文して分け合いつつ楽しむのが私の流儀ということで、2杯目に向かった。
2杯目は鴨醤油とりそばだ。焼きを入れた鴨と葱の香りや甘みがこれまた醤油によく合い、麺が中華そばではなく蕎麦でも違和感かない様な上品さと完成度があった。
連続で醤油系を頼むことを避ける選択肢もあったが、1杯目が非常に良かった為に、違いを感じたいという気持ちが勝って連続の采配を下した。
私の感覚としては、焼き葱と鴨の甘みと香ばしさによって、香りや舌触りは勿論のこと、甘みの方向性が違っていた。
もし1杯だけで終わらせる必要があるのであれば、その時の体調によってどちらを選ぶかは変わるだろう。
そして最後の3杯目は、味噌とりそばだ。
田辺市で作られた金山寺味噌とミンチ肉の入った、辛味の聞いた味わいで、添付のバターを混ぜながら味変ができるラーメンだった。
辛さを和らげる為にバターを使うというのは、何とも罪悪感のある食べ方と言うか、不健康な食べ方に思えてしまう。私が自転車に乗らなくなる日はまだ想像もできないが、その日が訪れたら、食べ過ぎに対してより注意深くならなければならないだろう。
この3杯目は、これまでの2杯とは決定的に違う刺激を感じたが、それは和食と中華の違いに近いレベルだったと思う。味噌、唐辛子、バターと、全体的にこれまでの2杯よりもパンチの効いた材料を使っている為に、後味として暫く残り、この後の宿への移動中は何度も思い出していた。
最後に一点だけ残った心残りは、基本的な塩味の鶏そばだけは注文しなかったことだ。その心残りは再び訪れる為の動機として心に燻らせておきたいと思う。
食後、店の前に泊まるバスを軒下で待っていたところ、バスが来たのだが、バス停のすぐ前にいなかった為か、そのまま我々をスルーして終点へと走っていった。
まだ予定時刻は過ぎていなかったので、不服ではあったが、仕方なく歩き出した。目的地もそう遠いわけではなかったので、食後の運動としてゆっくりと歩き出した。人通りの少ない田舎道は街灯も少なく、12月の日没後はほぼ暗闇で、雨音と川の流れる音が妙によく聞こえていた。
川湯温泉が近付くと、灯籠が幾つも吊り下がっており、12月の雨の日の肌寒い夜に、温かい明るさが浮かび上がっていた。
30分程歩いた後、川湯温泉そばの宿、すみ家に到着した。ここは前回に私が行けなくなった為、友人も一人で泊まるにはと思ったのか、泊まるのをやめたところだ。
今回、ようやく2人で来られて良かったと思う。田辺市の名産であり、なおかつ冬ということなのか、ミカンのサービスがあった。年末年始の道後温泉でも休憩所でミカンが置いてあったことを思い出し、冬の温泉はやはりミカンがよく似合うと思った。
川湯温泉は、これまで歩いてきた熊野川の支流である大塔川を掘ると湧いてくる温泉だ。70℃程の源泉が川の水と混ざり合って、ちょうど良い温度になったものを楽しめる。夏は川遊びの後に、冬は冷えた身体を温める為に入湯するのが人気だ。
基本的に年間を通して入湯できるが、12-2月の冬季限定で仙人風呂が開かれており、土曜日は20時から湯けむり灯篭イベントがあると聞いていたが、今回は雨が降ったからか、それを見ることは叶わなかった。
夜になるとやや肌寒い中、底から湧き上がる熱湯と川の水が混ざり合って、位置を時々変えながらぬる湯〜やや熱湯の範囲で楽しめた。
美味しいものをしっかり食べ、冷えた身体を充分に温めて、宿の布団も良い具合で、満腹ならぬ、満福と言える一日になったと思う。
翌日の解散予定のお昼過ぎまでの残り半日も、良い日にしたいと思いながら、翌朝までの良い無意識を過ごした。